ここではその気になれば誰でもが購入可能なものを中心に取り上げています
全国に普及していると考えられるもの、お店が発送を受け付けてくれるものを選んでいますが、一度注文したら、次回からは顧客番号で..などという「通信販売」のシステムが整備されているとは限りません。また、発送専用の電話番号もないところも多く、各店の電話番号を記載することに、わたしは抵抗を感じます。 代わりに、店の所在地や出店しているデパート等をお知らせしていますので、興味のある方は、後少し、手間をかけていただければ幸いです。
閉店、あるいは製造・販売中止等が明らかになった商品については、コメント色と商品タイトル色をグレイに切り替えていますが、消息不明も含め,存在しなくなったことが確認出来ない商品に追記措置はしていません。紹介日時を参考のうえ、経年にともなう情報劣化をご了承ください。
なお、各店のHPアドレスに関しては、確認日時を明記しました。
00/09/27(改稿 02/09/30 )
リストに戻る
 頂き物のミニトマト....パッケージラベルには勢登農園 アイコとありました。
頂き物のミニトマト....パッケージラベルには勢登農園 アイコとありました。
縦長のフォルムは、我家が知っているミニトマトとは随分違っています。もっとも、我家のミニトマト情報は相当前から進化していないので、アイコが最近出てきた新新種なのか、既におなじみになっているものかは分かりかねます。
実は、主人がミニトマトを好きではないので、我家ではミニトマトを買うことが無いままに過ぎてしまいました。とはいえ、外食や惣菜売り場でたまに目にするミニトマトはず〜っと、いつもの丸い品種でしたから、アイコは、多分まだ一般的なミニトマトではないのでしょうね。
パッケージを手にとってようやく、わたしはルスツリゾートの朝食ビュッフェで視界に入っていた、ちょっと『いびつ』な感じのミニトマトの品種に興味を抱きました。普段口にしないせいか、選択できる状態だと積極的には手をのばさないもので、ミニトマトの前は素通りしていたんですね。
で、ルスツHPの食材案内をチェックすると、ありました! 7月〜10月に提供される新種トマト 「アイコー」
(農園は違うようですが)アイコと同じと考えて間違いないでしょうね。
実際に食べてみての第一印象は、ミニトマトの野育ちさん(野育ちトマトについては、土佐のまほろばトマトを参照)風、でした。ミニでもしっかりとした歯ごたえがあって、ジューシーですが、水っぽさはありません。
 切って見ると、ゲル状部分が以外に少なくて、歯ごたえなりの肉厚さという納得の特徴が現れました。
切って見ると、ゲル状部分が以外に少なくて、歯ごたえなりの肉厚さという納得の特徴が現れました。
いわゆる外皮は、甘みの強い果肉(?)と一体化していて、嫌な舌触りもありません。
柔らかい皮の中から液体がとびたして、残った薄い皮が食感を損なうという....主人が好まないミニトマトのイメージを、アイコは一掃して、おいしいミニトマトの存在を知らしめたのでした。
特に産地が限定された作物ではないと思いますが、実際に食したアイコの風味が産地の恩恵を受けていることも考え、紹介にさいしてはエリアを特定しました。
10/09/12 ![]()
 一昨年の今時分、 自宅近くのデパートの小規模な北海道展でインカのめざめと言うじゃがいもの存在をを知りました。
一昨年の今時分、 自宅近くのデパートの小規模な北海道展でインカのめざめと言うじゃがいもの存在をを知りました。
前の年まで北海道民だったわたしたちは、きたあかりぐらいはきてるかしら? レッドムーンは無理だろうね〜などと冷やかし半分で立ち寄った場所で、初物に出会ってしまったわけですね。最初、今まできいたこともない名前を見て、北海道のモグリじゃないの?と疑わないでもありませんでしたが、収穫の少ない新品種との説明を受けて、一袋を購入しました。
思えば、流通し始めたばかりの頃だったのでしょうね...売り場のスタッフが、袋をあけてみては「似たたようなもんだけど...」と大きめのものを選んでくれましたが、それでも、親指と人差し指でできる輪を通り抜けられそうなミニサイスでした。ただ、鮮やかとも言える色合いとホッコリとした食感は、確かに印象的で、ほのかな甘みも美味でした。
2度目の出会いはそれから約1年半後の5月の千歳空港でのこと。
しかも魅惑的なことに、真空パック装丁のバタジャガになって、販売されていました。インカのめざめのバタジャガ表示にわたしが反応しないはずもなく、帰りのお土産に選定!
ところが、わずか3日後、それは影も形も、表示ラベルも値札も店から消えていたのです。聞いてみると、3日前にわたしが見たのが最後の入荷だったと言うではありませんか! そうと分かっていれば、イモを下げてトマムに向かったのに...と、後悔を引きずっての帰宅となりました。
 そして、北海道ではジャガイモの収穫期まっただ中の2004年10月、今度は逃すものかという勢いで店に向かうと、バタジャガは、予定はあるけれど、まだ先...とのこと。スタッフの印象では春先のアイテムだというのですね。でも...トマムでもインカのめざめの収穫の様子がHPで紹介されてましたし、収穫期が春というわけではないんですね。加工品になるのが春なのでしょうか...?
そして、北海道ではジャガイモの収穫期まっただ中の2004年10月、今度は逃すものかという勢いで店に向かうと、バタジャガは、予定はあるけれど、まだ先...とのこと。スタッフの印象では春先のアイテムだというのですね。でも...トマムでもインカのめざめの収穫の様子がHPで紹介されてましたし、収穫期が春というわけではないんですね。加工品になるのが春なのでしょうか...?
入手を諦めてトマムで過ごしたこれも3日後、帰路の千歳空港で偶然にみつけたのが、イメージのものでした。
きたあかりや男爵、メークイーンの箱と並んで、見覚えのある小ぶりの、でも北海道店で買ったものよりはかなり立派なジャガイモ、インカのめざめがありました。(大きさを玉子と比較してくださいね。)
1キロ単位での価格が表示されていたので、迷いなく飛びつきました。

バタジャガの代わりに生のイモを下げて帰って、レンジでチンしたのが左上と横ののイメージです。特色ある黄色みがお分かりいただけるかと思います。
1キロで10個...芋を手にキョロキョロしてたらどこかから出て来た売り場のおばちゃんが、計って袋に入れてくれました。1個平均は100グラムというところですが、一説によると、これ以上に大きくなると風味がおちるのだとか....。
芽が出やすい品種で、保存は原則冷蔵庫で...とされています。
この難点がなければ、箱で購入したいところですね。(常温保村が可能なバタジャガを見つけたら、買いだめしそう...。
)
04/12/06 ![]()
土佐の「まほろばトマト」
一昔以上前の話になりますが、当時住んでいた和光市の駅前にあったスーパーで、わたしは「これ、なあに?」というようなトマトを見つけました。
野育ちトマトと名付けられていました。通常のものよりもかなり小振りで、しかも、その大きさは不揃い、形もいびつで、黙って置かれていれば誰もが、規格外の半端ものだと思うに違いない商品でした。
ところが、お値段は一級品なみで、比較的大きめのものがふたつ、より小さいものはみっつ入ったパックが、ひとつ、598円だったのです。びっくりしたので、けっこうしっかり覚えています。
水やりを極力控え、あえて自然に近い厳しい環境で栽培することで、トマト自体の逞しい生命力を導き出しました。甘味がつよく、濃い、自然に近いトマトの味です。 と、いうような説明が、値札の横にありました。
主人もわたしも、自然の味を懐かしむ世代ではありませんでしたが、見た目の割りに強気の値段が気になって、買ってしまいました。 「おいしいに違いない!」と思ったのです。そして、その味は、期待も予想をも遥かに上回るものでした。甘い果肉はしっかりとしていて、芯の部分は緑色でした。
そうなると、野育ち以外の過保護トマトは、水っぽくて、食べられない。主人にかかると、へたを摘んでパックンひと口の大きさの野育ちトマトの為に、我が家のエンゲル係数は急上昇しました。ところが、もっと
不幸なことに、ある日突然野育ちトマトは店頭から、消えてしまいました。本当に、季節もの、だったのです。それからの数カ月、我が家は(ほとんど)トマトのない食生活をおくり、翌年の季節を待ちました。
引っ越しで、この店との縁が切れてから長い事、野育ちトマトは、一時の幻でした。
ただ、その間も、この栽培法法に着手する農家は増えていったようで、ある日突然、フルーツトマトという一般名で、市場に出回るようになりました。トマト画期的な栽培法法として、幾度かテレビでも取り上げられました。最初にこの方法を試したのは高知県の方だったことも知りました。
果物のような甘味がある、といわれるフルーツトマトは、見た目もお値段も随分マシになりましたが数年の間に厳しい環境にも慣れたとみえて、野育ちのようなパワー感じられません。
 まほろばトマトは、そうしたフルーツトマトの中のブランドのひとつです。
まほろばトマトは、そうしたフルーツトマトの中のブランドのひとつです。
通常のトマトのSSサイズくらいですが、大きさも形も整っていました。でも、針のように尖ったおしりは野育ちと同じで、少し固めの皮とパワフルな甘味は、他のフルーツトマトと一線を画している感じます。3月頃、スーパーではなく、デパートで見つかるかもしれません。
インターネットで確認を試みましたが、見つからないので、名称を変えた可能性もあります。
ネット上では、高知を中心に発送できるフルーツトマトの案内が多くでてきます。いずれもなかなかいいお値段ですが、感動に再び出会えるかもしれません。
00/10/04 ![]()
 イメージは3月26日に高知から到着した、土佐のまほろばトマトです。
イメージは3月26日に高知から到着した、土佐のまほろばトマトです。
最近ではフルーツトマトも得に珍しくはなくなって、この季節にはスーパーでもよく見かけますが、宮崎や熊本産のものが多いようです。それはそれで、おいしいものの、今年は思いきって高知から取り寄せました。
徳谷トマトほど高くはないまほろばトマトですが輝く赤い色の中からは、深い緑の果肉があらわれます。(左下イメージ)しっかりと凝縮されたような甘味も期待どおりでした。
店頭で探すよりも、インターネットで検索したほうが、出会える確率は高いかもしれません。
小振りなので、おそらく主人は、ひと口でパックンでしょう。1.5キロのトマトを、新鮮な内に消費できるかという不安もありましたが、到着直後に味見をして(右下、イメージを撮る前に、ひとつ、わたしのおなかに消えました。)その心配も吹っ飛びました。
01/03/26 ![]()
錦水亭の「たけのこのつくだ煮」
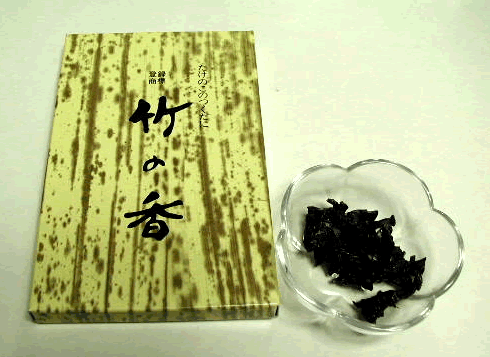 錦水亭は京都にあるたけのこ料理の専門店です。
錦水亭は京都にあるたけのこ料理の専門店です。
ず〜と前の5月の連休の頃に、たけのこのコース料理を食べに行った事があります。たけのこの木の芽あえ、たけのこのおさしみ、
たけのこのステーキ、たけのこの田楽、たけのこの酢の物、など、京都のたけのこを思う存分食べさせてくれます。
たけのこの旬ではない季節はどうしているのかしら、という疑問は解決されないままですが....、この店のたけのこのつくだ煮は1年中味わうことができます。
ビン入りと袋入り(箱入り)があって、どちらも日持ちがします。重宝します。
昨年末に送ってもらった商品の賞味期限は今年の11月30日でした。たけのこのつくだ煮、たけのことしいたけのつくだ煮、たけのこときくらげのつくだ煮の3種類があって、お値段は同じです。
つくだ煮ですからしっかりとした味ですが、そこは関西の名店、くどさなどとは無縁で、いくらでもいただけます。
デパートでは高島屋の日本橋店と難波(大阪)店の地下、ふるさとの味コーナーで取り扱われています。お願いすれば、送ってもらえます。
そのコーナーには他に、高野山のごま豆腐や三島亭の牛肉のつくだ煮などもあって、一緒に発送してもらえますから、それぞれの店に直接注文するよりお特でお手軽です。
イメージは、たけのこのつくだ煮の袋入り(折りたたみの箱の中に真空状態の袋が入ってます。)、内容量140グラムで 800円でした。
00/09/27 ![]()
村上重本店の「つぼ漬け、大根の柚子風味漬け、千枚漬け」
 京都、四条の阪急デパートの裏手に村上重本店があります。
京都、四条の阪急デパートの裏手に村上重本店があります。
雰囲気のあるその店の前を通ったのは、偶然でした。
「むらかみ...」と店の名前を確認するより早く、主人が一言。
「お、ココ、ヤマモトマスヒロさんの推薦の店だ!」
「ホント?」
特別に記憶力がいいというわけではないのに、主人はなぜかこのての話は得意です。覚えていると言うより思い出すようですが、思い出したデータはおおむね間違いがありません。
わたしたちは、多くの種類の中から主人の記憶に従って(お勧めの)大根の柚子風味漬けと、季節柄千枚漬けはなかったので、つぼ漬けたくあんを買いました。
柚子大根というのも京都独特のものでしょうか? 千枚漬けと同様、他の地方では見かけませんね。
お味の方は、まろやか、の一言です。
この時以降、何度か、京都の他のいくつかの店の柚子大根を(手に入り易いということで)いただく機会もありましたが、違いはハッキリとわかりました。もともと日持ちはしない柚子大根ですが、1日経つごとに酸味が強くなります。他の多くの柚子大根は、3日経った村上重のものよりまだ味がしつこいと思って下さい。もちろん、全国に展開している京都のお漬け物は、日持ちをよくする
為に工夫がされています。その為に使われているかもしれない余分なものが影響しているのかもしれません。
つぼ漬けたくあんは若干日持ちがします。あまりに(味に)差があるので、わたしは何年もの間、この店意外のつぼ漬けは食べていません。べったら漬けやはりはり漬け...といった、比べることのできないものをいただいてます。
デパート等で開催される「京都の物産展」などで、村上重本店のお漬け物に出会うことはまれです。
大阪、難波の高島屋、東京、新宿の高島屋の日本の味コーナーで、常時取り扱われています。
京都、四条の村上重本店では発送の依頼にも慣れた様子で対応してくれます。一度お願いすると、ギフトシーズンには、簡単なパンフレットと案内が届きます。
00/10/13 ![]()
遊味館のこだわりスープの「ごぼうのクリームスープ」
 京都在住当時に、月に2度ほど利用していたスーパーからの帰り、路を1本間違えた為に、その時まで気がつかなかったスーパーに遭遇しました。いかにも地元の店という感じのその店に、大手スーパーの大量仕入れでは叶わないこだわりの何かがあるかもしれないと期待して、入店。 見つけたのがごぼうのクリームスープでした。
京都在住当時に、月に2度ほど利用していたスーパーからの帰り、路を1本間違えた為に、その時まで気がつかなかったスーパーに遭遇しました。いかにも地元の店という感じのその店に、大手スーパーの大量仕入れでは叶わないこだわりの何かがあるかもしれないと期待して、入店。 見つけたのがごぼうのクリームスープでした。
京都生まれ、遊味館のこだわりスープというのが製品名のようでしたが、スーパーというよりも八百屋さんの雰囲気があった店内の棚には、ごぼうのクリームスープだけが納品時に入っていたと思われる箱のまま陳列されていました。わたしが店に期待したこだわりの真偽はともかく、新商品との出会いは叶ったわけですが....ただ、このスープ、180円だったんですね。相場よりも安いか高いかは別として、180円で感動がついてくるでしょうか...?
これがコーンやポテトのスープなら、わたしは買わなかったと思います。
でも、ごぼうです!
ルミエールで食して以来、ごぼうのクリームスープへの執着が続いているものの、製品に出会う機会がなかったせいで、この時は存在そのものが感動だったんですね。おいしくなくてもそれはそれ、のつもりで買って帰りました。
ところが、予想に反して、180円で得られた感動は大きかったんです。
我が家の好みでは、気持ち、5%ほど塩加減が控え目な方がベターという不完全さはありましたけど、香りも味も繊維質のざらつき加減も申し分ありませんでした。何よりもうれしかったのは、(細かな繊維質が残っていてさえ)仕上がりがサラリとしていたことで、素材が活きたしっかりとした風味に軽い口当たりが絶妙でした。
でも、これは我が家の定番になると思い、再び立ち寄ったスーパーには、そこにこのスープがあった痕跡は何ひとつ残っていませんでした。箱も、スペースも、値札も....。1度や2度の経験ではありませんから、わたしもたくましくなりました。こういう時は、焦らず騒がず、パッケージに記載の販売元に問い合わせるのが早道です。ただ、最初に買ったスープの袋に明記されていたのは、住所のみで電話番号がなかったので、手紙を書くよりも地道なネット検索に時間を費やし、商品取り扱いサイトにたどり着くことができました。
スープは他にもエビ風味のクラムチャウダー、トリュフ入りきのこのクリームスープ、さつま芋と栗のスープなど数種類が紹介されていました。商品説明に遊昧館と明記されているものもされていないものもありますが、すべて遊昧館のこだわりスープのシリーズです.(上記イメージ)
ごぼうのクリームスープの感動の再現を狙って、各種取り寄せてみましたが....他は割合にドロリ、トロ〜リとした仕上がりで、それなりのおいしさでした。最初に出会ったのがごぼうのクリームスープでなければ、縁を繋ぐ努力はしていなかったかもしれません。
機会があれば、まず、ごぼうのクリームスープからお試しくださいね。
(大阪、京都ではまれに店頭で見かけることもありますけど、入荷の主流はカボチャ、コーン、じゃがいものスープのようです。)
http://www.powercom.co.jp/gensenshokuhin/ (2004年4月8日確認済み)
04/04/09 ![]()