おまけのページ、“EXTRA”の第2回目のテーマとして展開した紅茶の話は、2002年4月、晴れて独立することになりました。
今後はCONTENTSかHP内に点在する紅茶専用ボタンを御利用のうえ、雑談におつきあいください。
専用ボタンは紅茶関連の全リスト にリンクしています。
2004年05月14日
紅茶に関係するエピソードのページです。
本編の横におまけのようにくっついていた思い出話や、補足情報もこちらに移行し、単独でもご覧いただけるように一部改稿しました。本編と直接関連のあるものはその旨お知らせしていますので,合わせてご覧くださいね。
そういえば...こんなことがあったよねという過ぎた体験談からリアルタイムのプチレポートなど、規則性のない雑談をお楽しみください。時に...お役に立つ話もあるかもしれません。
04/05/15 ![]()
フォション フォーション、フォーチュン
あと数年すれば、ふた昔前の話ですが...という頃、旭川の買い物公園通りで“フォーション”という名前の喫茶店を見つけました。
「フォションの紅茶を、置いてるとか?」「まさか...。」といいながら、店名に興味を覚えて入ってみると,店内奥の厨房の棚には、金色のフォションの缶がズラリ!
マリアージュ・フレールの存在すら知らなかった時期で、アップルティーをはじめ、香り付けされた紅茶を多く扱うフォションは、当時のわたしのお気に入りでした。フレーバードティーが好きだった、というより旬の物に敏感だっただけかもしれませんが、通常は高島屋でしか買えないはずの“レアもの”に旭川で出会えたことは驚きでした。
だって、フォションの紅茶をお店で飲むのは、その時が初めてだったんですから。
旭川ではコーヒーが300円台の頃に、シリンダー式のポットでサービスされる紅茶が500円台のお値段設定でしたが、紅茶を雰囲気楽しむ傾向があったわたしは、割高のお値段にも、妙に感動したものです。
「旭川はね、北海道第2の町って言ったって、田舎ですよ。でもこんな田舎でもね、一流の味を味わえればね、そういう味を知って欲しくて、店を始めたんです!」
わたしたちのリアクションに感じる何かがあったのか、若い店主が 、一見の客を相手に熱い思いを語ってくれましたが....3年くらい経って通った時、そこに店はありませんでした。
トワイニングでもフォートナムメイソンでもなく、フォションを選んだ店主のこだわりの行方がちょっと気になりました。
気になったと言えば、フォーションと言う店名。
当初、フォションを無断では使えないので,フォションをイメージさせるフォーションと言う単語を作ったのかと思っていましたが、フォションがポピュラーになるに従ってフォーションと言う言葉を耳にする機会が増えました。フォションのことをフォーションと言う人が少なくないんですね。
缶のラベルには,カタカナでフォションと書いてあるのですけど,目よりも耳で覚えた結果でしょうか...?
近いところでは母もフォーションと覚えたみたいです。
「フォションだよ。のばさないんだよ。」とわたしが訂正を試みても「はいはいフォションね。」と言いつつ、切り替えはきかないんですね。そのうちに「ああ、もう、どっちでもいいじゃない。通じるんだから。みんなフォーションって言ってるもん。」と逆襲されたことがあります。
....ま、いいですけどね。確かに、通じてるんで...。
ファストフードがファーストフードになるくらいだから(何が First なのかと疑問を抱いたこともあるわたしは、スローフードという言葉の登場で、ファーストはファストの日本語なまりなのだと勝手に理解して、スッキリしました。わりと最近のことです。)フォションをフォーションと言って、問題があるとも思えませんものね。
でも、これも北海道の,旭川近く、層雲峡のとあるホテルのラウンジで「フォーチュンの紅茶あります。」と書かれたメニューを見せられた時には、やっぱり固有名詞は正確に覚えた方が....と思いました。
FAUCHONをカタカナに直した結果と推察しますけど、フォーチュンではパリの紅茶もちょっと気の毒な気がしませんか?
04/05/14(改稿)![]()
リストに戻る 紅茶全般のリストを見る
紅茶の本
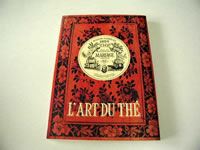 マリアージュ・フレールとの出会いを提供してくれた学園都市のティールームは、その後、路線変更とリニューアルを繰り返し、取り扱う紅茶も変わりました。
マリアージュ・フレールとの出会いを提供してくれた学園都市のティールームは、その後、路線変更とリニューアルを繰り返し、取り扱う紅茶も変わりました。
マリアージュの茶葉を取り扱う店が近くになくなった為に、
わたしは、代理店(当時の代理店は紅茶専門店「レピシエ」になりました。「マリアージュ・フレール」は直営店として、青山から銀座に移りました。)に電話をして通信販売で、茶葉を購入する生活になりました。
お茶のサンプルプレゼント、情報紙の配布など、通販のメリットを知ることができたのは、地方住まいだったから....?
紅茶の本は、何かのキャンペーンの時に、おまけで入ってきたものです。
紅茶に関する決まり事の多くを、わたしはこの本から学びました。
本はマリアージュのティーカタログをかねていて、それぞれのお茶の特色等も記載されています。毎年発行されるものでもなさそうで、品番と名前と価格が並んだのリストにある新商品が,本には載っていないことも....。
一昨年買い直した本は、それよりも2年くらい前に編集されたものとかで、時間差による情報不足が残念です。
04/05/14(改稿)![]()
リストに戻る 紅茶全般のリストを見る
お茶の価格とグレード
本編、グレードの基本は葉っぱの位置 茶園は一種のブランド 安心を買うか、自分の舌で見極めるか...参照)
手もとにティーリストがある為、グレードとお値段の関係の具体例として、マリアージュ・フレールのお茶を上げていますが、これらはパリに寄り道してくるので、お値段はやはり高めです。
参考までに、10000円の“キャッスルトン”のパリでのお値段は38.50ユーロでした。パリから日本までの道のりで、この価格差! ため息ものですね。
言い換えればパリ本国では農園別、摘み取り期別のダージリンであっても10ユーロ、20ユーロ前後で購入できる物が多くあるんですね。例えば春摘み21種の内、10ユーロ以下のものは5種、10ユーロから20ユーロ以下が7種、25ユーロを超える物が5種という内訳(2003年ティーリスト)です。
代理店契約でマリアージュ・フレールの茶葉を販売していた前身を持つレピシエが、直輸入、直販主義を宣言して小売業を始めた当初、“キャッスルトン”は春摘み、夏摘みともに100グラム3000円でしたから、マリアージュ・フレールのパリ価格と比較しても、納得のお安さでした。
ただ、この時レピシエの取り扱っっていた“キャッスルトン”のグレードはFTGFOPで、マリアージュ・フレールのものはSFTGFOP......うれしい価格は直輸入のメリットとグレードの違いというところでしょうか。
今にして思えば、1995年のレピシエの、例えば春摘みダージリンの価格帯は感涙もので、100グラム3000円だったのは14アイテムの内,“キャッスルトン”と“ピュッタボン”と“リントン”のわずかにみっつ...2500円の“セリムヒル”を除いた他の10アイテムはすべて1000円台でした。
9年経過すれば,値上がりもやむなし...かもしれませんが、ブレンド、フレーバードティーに限らず,産地、農園限定のものでも大半の茶葉の価格はほとんど変わらない(50グラム単位になって,むしろ安くなっているものも...。)のに、ダージリン、特に春摘みは、びっくりするくらいに高くなってしまいました。そのうちに、上陸当時から今日まで変化なしのマリアージュ・フレールの日本価格に追いつくかもしれない勢いで、幾ばくかの反発さえ感じてしまいます。 良いお茶を直輸入でより安くという、小売業転身時のポリシーは、どこに置いてしまったのでしょうね?
ところで、産地、農園特定の紅茶につきもののアルファベット....日本では茶葉のグレードという言い方をされていますが、グレード...いわゆる等級ですね。素直に解釈すれば茶葉のランク付けのはずで、実際にアルファベットの多いもの≒グレードの高いもの≒お値段の高いものという関係が成立しているのですけど、紅茶の解説本かなにかで「グレードは茶葉の形状示すもの(抽出時間等の参考の為のもの)であって、品質の優劣とはちがう」と言うアドヴァイスを目にした方も多いのでは...と思います。わたしも,かつて立ち読みでこの種の解説を見た記憶があります。
なにぶん立ち読みですから、読解力に問題があったのかもしれませんが、グレード(等級)と品質とは別のものという説明に非常な違和感を覚えたものでした。だって...マリアージュ・フレールのティーリストを見るかぎり、グレードは品質のランクそのものでしたから...。
そのマリアージュ・フレールの、90年代前半のお茶の本の日本語版には、下記の記述があります。
「紅茶の専門家は,お茶を分類するのに,茶葉の質のみを重要視しています。葉が砕いてあるとか、細かく挽かれているとか,完全な形であるとかにとらわれません。なぜなら、それらは質的に何の変わりもないからです。」
つまり、茶葉がフルリーフか,ブロークンか...その形状と品質は無関係だけれども、茶葉はその品質によって分類されているわけで、アルファベットで表されるグレードと品質には、強い関係があります。
グレード(等級)一覧を掲載して、ただし品質とは無関係などと言う記述を見かけると じゃあ、ど〜して、アルファベット文字がたくさん付くほど、価格が高いのよ? ど〜して、スペシャル(一番左につくS)なんて単語がでてくるのよ?と追求したくなりますが,店頭の本よりはここは,再び,マリアージュ・フレールのお茶の本、改訂版!
分類と品質の関係について、もう少し分かりやすく書き換えられています。
「紅茶は、茶葉の状態に応じて分類がされます。この分類とは茶葉の品質のことではありません。茶葉が粉状であるのか,砕いてあるのか、フルリーフ,と言う形状別の分類ですから,この分類において,茶葉のクオリティーはどれも同じです。」
例えばTGFOP(ティッピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ)とTGFBOP(ティッピー・ゴールデン・フラワリー・ブロークン・オレンジ・ペコ)はフルリーフかブロークンかの違いだけで、品質は同じと言うことになりますね。
TGFOPとFTGFOP(ファイネスト・ティッピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコ)は、茶葉の形状は同じフルリーフ、品質は違います。
本編でわたしが形容詞と称した部分が品質の分類とすれば、右よりの記号は茶葉の形状(フルリーフ、ブロークン『B』、 ファニング『F』)と部位(フラワリー・オレンジ・ペコ『FOP』、オレンジ・ペコ『OP』、ペコ『P』、ペコ・スーチョン『PS』、スーチョン『S』)....となれば、グレードは品質と形状をともに分類した記号と解釈するのがベターだと考えます。
ただ、今では紅茶の基礎知識のように取り扱われているグレードが、各国の(紅茶の)消費者に広く認知されているのかといえば、わたしはそうは思いません。レピシエ初期のパンフレットには、「ヨーロッパ人は...グレード分けしました。」とありますけど、ヨーロッパの紅茶メーカーといえば、英国ブランドほどポピュラーではありませんし...実際に、紅茶のグレード表示をして販売している海外のメーカーを、わたしはマリアージュ・フレール以外に思い起こせません。マリアージュ・フレールと同じパリ生まれのフォション、エディアールにもグレード表示は、基本的にはありませんしね。
あるとすれば,例えばフォートナム・
スペシャルやファイネストの形容詞が付くグレード表示は、産地や農園限定茶葉の、クオリティのお墨付きにたいなものですから、その種の茶葉が流通する範囲において,かなり限定的に使われている気がします。つまり、マリアージュ・フレールと、この10年ほどの間に登場した、日本国内の多くの紅茶専門店で...ですね。
SFTGFOPやFTGFOPのようなグレードの茶葉が、いたるところ、しかも複数の店で取り扱われてるなんて....
日本の紅茶事情はものすごく特殊な環境にはまっちゃったのかもしれませんね。
わたし自身は,ダージリンの春摘みフリークですから、この環境を喜ぶべきなのですけど....でも、お値段を考えると,良い環境とは言えそうもありません。
蛇足ですが、パリのマリアージュ・フレールでは通販ダイヤルも、オーダーフォームもちゃんとあって、世界のどこにでも発送してくれるそうですが、唯一、日本だけが例外国で発送不可! 今やパリ本国よりも店舗数の多いマリアージュ・フレール・ジャポンがあるから,そちらで買ってね、というわけです。
35.50ユーロのキャッスルトンを、10000円で買わなくてはいけないのは...わたしたちだけ..なんですね。
04/06/15(改稿)![]()
ティーコゼー不要のティーポット
右イメージは、我が家で使用頻度が一番高い、マリアージュ・フレールのオリジナルティーポットです。
マリアージュ・フレールのサロンでも使われていますし、販売もされているので、直営店利用する機会がある方にはお馴染みかもしれませんね。
“アール・デコ・マリアージュ・フレール”と言うシリーズ名がついているようで、色は、黒の他に白と柑。サイズは2種類で、こちらは1〜2人用の小さい方で,容量は0.9リットルです。(3〜4人用は1.3リットル)同じマリアージュ・フレールオリジナルのティーカップを基準にすると、約6杯分....おかわり1回で済むゲストなら3人まで、このポットでもなんとかいけそうですね。(サロンではこのサイズはあくまで1人用として使われてます。)容量1.3リットルのものは、大きさ、重さともに使い勝手に問題がありそうで、量が必要な時には,わたしはポットふたつにわけています。
紅茶を日常的に飲むようになって、ポットの必要性が高まった時に、我が家では迷うことなくこのポットを選びました。
マリアージュの茶葉を取り扱っていた学園都市のティーサロンで使われていたので、使い勝手も納得済み。
驚くべき保温力と適度な重厚感、そしてティーカップを選ばないシンプルな美しさに“ひとめぼれ”だったんですね。ポットが第一の候補にあがりました。
 保温力の秘密はステンレスカバーの内側に貼られたフェルト....でしょうか?一般的なティーコゼーよりも機能、能力ともにすぐれています。
保温力の秘密はステンレスカバーの内側に貼られたフェルト....でしょうか?一般的なティーコゼーよりも機能、能力ともにすぐれています。
ティーコゼーを使うお茶の時間に、一抹のあこがれを抱いていたわたしとしては、意外な選択でした。
でも、ティーコゼーを使うティーサロンが増えて、あこがれを体験する機会が多くなると、ああ...これ、結構鬱陶しいなあという実感もあったんですね。かぶせるタイプのは、お茶をそそぐ度に、はずしたりかぶせたりを繰り返すわけですけど、ポットと分かれたティーコゼーは、その間、単なる邪魔者になったりするんですね。
サイドテーブルなどがある環境ならともかく、大半のサロンでは、外したティーコゼーを自然に置けるほどテーブルにスペースがありませんし、そういう空間ではティーコゼーの着脱行為自体がストレスになることがありました。
また、ポットのボディーを包み込むタイプのティーコゼーは、着脱不要のメリットがありますけど、ポットのデザインとの相性を考えなくては....。例えば、ハロッズのグリーンに黄色のストライプ柄のティーコゼーから、ジノリのイタリアンフルーツ柄のポットの口と把っ手が出てたのでは、センスのいいコーディネイトとは言えませんものね。
センスを磨いたり、優雅なティーコゼーさばき(?)を習得する頑張りがきかなくっても、マリアージュ・フレールのポットがあれば平気!というわけで、わたしは安易な選択をしたのかもしれません。
でも,10年使い続けてみて、ひとめぼれの選択は正しかったのだと感じ入っています。
蛇足ながら、黒を選んだのは、汚れが目立たないから...。本気で安易な選択でした。
水色を見るためには、言うまでもなく 白ポットがおすすめです。
04/07/31 ![]()
リストに戻る 紅茶全般のリストを見る
ティーポット(抽選に当たる確率)
 1994年、マリアージュジュルナルNO24(6、7月合併号)紙上で、マリアージュ・フレール140周年記念の抽選会の案内が記載されました。
1994年、マリアージュジュルナルNO24(6、7月合併号)紙上で、マリアージュ・フレール140周年記念の抽選会の案内が記載されました。
6月1日から7月31日の期間中に通販での注文,店頭での買い物5000円毎にもらえる抽選券に必要事項を記入して応募すれば、ポットや茶葉が当たるかもしれないというもので、ポットは6種類、各5名、100グラム缶入りの茶葉が50名に、残念賞は500円のギフトカードで、こちらは1854名にと言う商品ラインナップでした。
たまたま青山店で買い物をする機会があったわたしは、店頭で記入した抽選券を預けてはきたものの、当たる気がしないというのが正直なところで、抽選会の件はそれきり...のはずでした。
ところが7月の終わり近くなって、通販で茶葉を取り寄せた際、なぜか抽選券がサービスでたくさん同封されていまして、応募して下さいね、みたいなコメントも添えられていたのです。1枚、2枚なら無視してたかもしれない状況ですが、購入金額以上に抽選券をにいただいてしまったことで、わたしも、義理は果たさなくちゃの気分になったんですね。
せっせと住所、氏名を記入して、さて、どのポットにしようかと思案中(ポットは6種類の中から一つを選んで応募するのでした。)のところに、同じ時期に茶葉をオーダーしたお隣さんが、5000円分も買っていないのに、抽選券が入っていたと言って、持ってきてくれました。1枚だけ送り返す(抽選券は封書で返送)のもかなんだから..「あげる。」と言うのです。99%、当たらないことを前提にした話でした。でも、1%の部分で当たっちゃったらね...自分の券で当たったのか、頂き物の券が当たったのかが特定できないだけに、もらったわたしも多少の抵抗が残ります。で、一緒に郵送してあげるからと、わたしはお隣さんにも応募することを勧めました。
封筒の中には1枚だけ、名前の違う抽選券がまじってマリアージュ・フレールに届いたことになります。
そして、その結果、わたしたちは二人そろって、30名の当選者の中に名を連ねたのでした。
当選者の発表はジュルナル紙上でということでしたが、実際にはポットの当選者の氏名と居住都道府県形が記載された切り抜きがジュルナルに同封されてきました。6種のポットのイラストの上に、それぞれ5名づつの名前が並んでいたのですけど、自分の名前がレジェンドポット(右上イメージ)の当選者の一番上に見つけてびっくりしたわたしは、その直後、隣のマハラジャポットにお隣さんの名前があったので、我が目を疑いました。
30名中、北海道から当選したのは2名だけで(当時は、我が家は札幌在住)、その2名がよりによって隣同士なのですから、まさに「信じられない!」の連発でした。
一緒に送ってもらって良かった、とお隣さんには感謝されました。
こんな偶然はありえないので、わたしが(たくさん応募したので)当選した段階で、隣のよしみで自分もくっつけてもらえたに違いないというのですね。
抽選はもちろん公正に行われたはずですが、お隣さんの解釈さえ検討事項になると........思えてしまう珍事でした。
04/08/13 ![]()
リストに戻る 紅茶全般のリストを見る
紅茶に最適の天然水
(本編 フィルターを使ってお茶をいれる 英国式の差し湯で、お茶は
おいしくなる? 参照)
 左イメージは2000年の夏にレピシエから新発売キャンペーンで送られて来た「お茶がおいしい天然水」。
左イメージは2000年の夏にレピシエから新発売キャンペーンで送られて来た「お茶がおいしい天然水」。
国内の天然水の中から探し当てた、お茶にあう水で、レピシエのティーサロンで使っていること、そして特にダージリンの春摘み、半発酵茶、緑茶に最適というコメントが添えられていました。紅茶は完全発酵茶。そしてこの水は軟水(でした).....ということは、なるほど、つまり軟水は発酵の浅いお茶により合うということか....なるほど、なるほど。ものの本には紅茶に最適なのは軟水とあるけれど、ベストマッチなのは紅茶よりは緑茶...とすれば、イギリスの紅茶がおいしいのは水が違う(硬水)から(よく聞く...気がするのは、わたしだけでしょうか?)という理由づけも、的外れではないことになりますね。
でも、こだわりのアイスティーの特集のレピシエだよりVol.054(2000年7月号)には、販売を開始した天然水のことが,もう少し詳しく紹介されています。
長野県木曽福島町、標高800Mの地点に水源となるわき水を、現地でボトルにつめただけの「お茶がおいしい天然水」は産地直送アイテム。1ダース、あるいは半ダース単位の通販ものなんですね。
産地や発酵度、フレーバーの別を選ばず、あらゆるお茶の個性をのびやかに引き出してくれる素直な天然水だそうで、レピシエだよりには特に春摘み、半発酵茶に...というフレーズはありませんでした。
あった方が、わたしとしては気分が落ち着くのですけど、春摘みや緑茶よりも、遥かに多くの(春摘みではない)紅茶をもレピシエではこの天然水でいれているということで、まさに万能水...。
茶葉の種類によって水を変える程のこだわりが現実的ではない以上、成分が出やすい軟水の方が硬水よりも適しているのは(今は)理解できますが...軟水を薦める様々な場面で、実は紅茶がおいしいとされるイギリスの水は硬水ですが...という事実にも言及してくれることがマレなことは残念です。
たとえば、フォートナムメイソンのロイヤルブレンドを英国式ルールに基づいてこの水でいれたとしたら、おいしいのかなあ...? 渋みが出過ぎて,差し湯も甲斐なし...ってことになりませんかあ〜?と、あまのじゃくなわたしは、つい、万能水のリスクを想像してしまいます。
レピシエには、サロンで天然水を使用していることと同時にティーフィルターを使用もアピールしていただかなくては、片手落ちのように思えますね。
04/10/05 ![]()
リストに戻る 紅茶全般のリストを見る